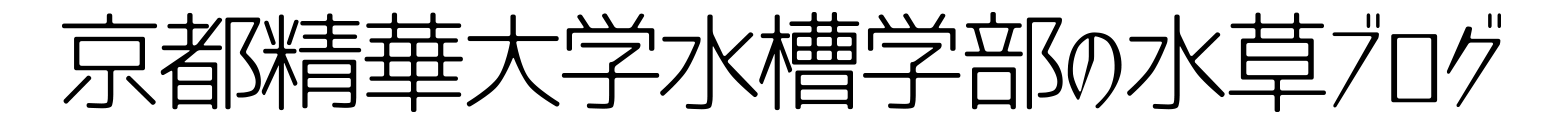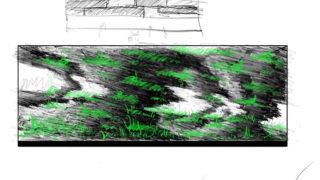ゴホン!顧問のタナカカツキでございます。
年末、みなさんいかがお過ごしでしょうか?
学部員のみなさまから、斬新なレイアウト案をたくさんいただきました。
図案スケッチをみてるだけでも楽しいですね。
顧問も含め、まだまだ水草レイアウト水槽については知らないことばかり
知らないおかげで奇抜で突飛な攻めの図案が生まれます。
図案を見ながら、このレイアウトはどうやって維持管理すればいいのか
現実問題が立ちはだかります。
ただのお行儀の良いだけのありがちなレイアウトにしたくない。
人の心を掴む「印象」や「独創性」も重要なエッセンスなので忘れないようにしたい。
奇抜、突飛、攻め、センセーショナル、エキセントリック… イメージは駆け巡りますが
私たちはいつまでも素人でいられるはずもなく
一見、ごく普通のレイアウトから独創性を感じる目を獲得してしまうかもしれません。
いつまでも私たちは無知でいられません。
水草のこと、水質のこと、生態系のこと、知っていきましょう。
知ることで、これまでに体験してこなかった造形感覚
自然に寄り添うことで、今まで感じたことのないデザイン体験があるかもしれません。
自然に目を向ける態度はデザインの直接体験だと顧問は考えます。
水草をレイアウトする、ということ
一部のマニアックなアクアリストや、熱帯魚ショプの店員さんだけのものではありません。
むしろ、私たち、デザイン学部に与えられた新時代の水のキャンバス
水草レイアウトはデザイン大学に任せろ!という鼻息で
挑みたい表現分野ですね。

「水草水槽」
それは、部屋のインテリア、癒し、ホビー、さまざまな在り方をしておりますが
わが水槽学部では「水草水槽」を芸術として迎え入れたいです
なぜなら、そこにはあらゆる美のエッセンスが盛り込まれているからです
ガラスケースの額縁、水のキャンバスに、水草を絵の具にした生きた絵画です
流木や、石、魚も重要な素材です
アクア機器の進化、底床の発明、ネットコミュニケーションによる情報の共有
現在だからこそ出てきた表現であり、現代の絵画表現です。
デザイン学部としては、この新表現に挑まないわけにいきません。
モネや、印象派の画家たちが、もしも、今この時代に生き
それらの新しい水の絵画ことを知ったらどんな反応をしたでしょう。
彼らの時代、水草や光、水のゆらぎ、自然にあるものをそのまま部屋に持ち込み
それを維持できる技術や道具はありませんでした。
物理的な自然をアトリエに持ち込めない、できないという前提がある中で
布キャンバスに色の液体を塗る技法によりその印象をキャンバスに定着させてゆきました。
それにより、豊かな絵画の歴史が広がってゆきましたが
もしその時代、水草水槽があったなら、彼れはそれを無視できたでしょうか?
光を追いつづけた表現者としての姿勢を
2010になった今、やるとしたら、どんな表現が考えらるでしょう。
美とは、デザイン、レイアウトとはどんなものなのか
私たちは問わずにはいられません。
水草レイアウト水槽は、自然を知り、手を濡らし、芽吹く命とともに
学ぶことができる豊かなザイン教材と考えます。
次回、仕切りなおしまーす!w