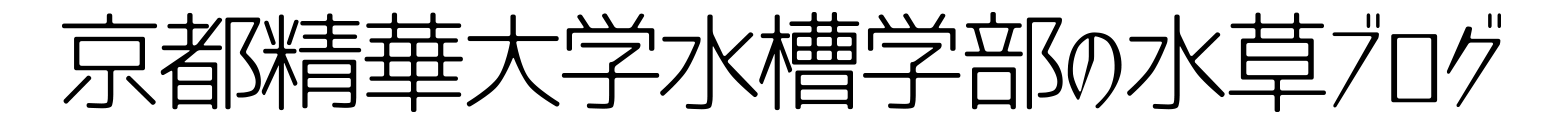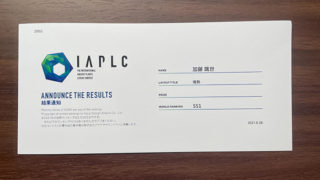顧問のタナカカツキです
私が水草水槽の存在に気づいたのは、2010年頃のことでした。
それまではアクアリウムを趣味にするなどまったく考えたことがなく
「水槽なんて面倒なだけだ。手を出すべきではない!」と胸を張って思い込んでいたのです。

もちろん、部屋に美しい熱帯魚が泳ぐ水槽があれば素敵だろうと感じる気持ちはありました。
しかし、生き物を飼うには相応の覚悟が必要で、単に「かわいい」というだけで済む話ではありません。
お金も手間もかかるでしょうし、何よりそんなことに時間を費やすのはもったいないと考えていました。
深夜に仕事から帰宅し、部屋の明かりをつけずに水槽を眺めて癒やされるなんて、いかにも疲れた現代人らしい行動のようで、どこか気恥ずかしくもあったのです。
ところが、あるとき何気なく金魚について調べてみたところ

思わず笑ってしまうようなユーモラスな顔立ちの金魚を見つけ、一目で心を奪われてしまいました。
まるでマンガに出てくるキャラクターのような愛らしさだったのです。

ご存知の方も多いように、金魚の品種改良は驚くほど多岐にわたります。
日本では金魚の美しさや優雅さを求める改良が重ねられる一方、中国では形の面白さや変わった姿に重点を置いた改良が進められてきました。そうした国ごとの趣向の違いも、実に興味深いものです。

交雑や突然変異の誘発、人為的な選択など、さまざまな手法には問題もあるとはいえ
長い歴史と文化を背負った“金魚芸術”を部屋で眺めてみるのは、新たな発見や思考を呼び起こすきっかけになるかもしれません。
観賞魚としての歴史は1000年近くにおよび、その間、絶え間なく品種改良が繰り返されてきました。
そんな小さな赤い伝統の揺らめきを自分の部屋に迎え入れることに、私は思いがけず惹かれてしまったのです。

そして気づけば、伝統美という引力に導かれるようにして
水槽の世界へと足を踏み入れてしまっていました。

つづく!